簿記3級の「決算整理」で「未払費用」と「未収収益」がどういうものか、混乱しやすいポイントを含めて、わかりやすく解説します!
「なるほど!」と思ってもらえると嬉しいです。
はじめに
簿記3級を勉強中の人なら、「決算整理仕訳(特に経過勘定)」でつまずいた経験、多いんじゃないかな?
その中でも、「未払費用」と「未収収益」は名前も似てるし、何をもって仕訳するのか・貸借対照表や損益計算書にどう影響するかが分かりにくいところ。
でも、ここをきちんと理解できれば「決算整理謎の壁」がだいぶ低くなる!
この記事では、簿記3級レベルで必要なことを中心に、「未払費用」と「未収収益」の意味・仕訳パターン・試験でよく出る例・混同しないコツをていねいに解説します。
経過勘定とは何か?決算整理で“わかりやすく”押さえるべき考え方
発生主義と見越・繰り延べの考え方
- 簿記・会計では「発生主義」というルールが基本。義務や権利が発生した時点で費用や収益を認識する。現金の出入り(支払い・受取)が後でも前でも、サービスやモノの提供があれば“発生”として扱う。
- 決算整理仕訳には「見越」および「繰延」という処理が出てきて、これを使って発生主義・実現主義との差を調整する。
経過勘定の4パターン
決算整理で出てくる代表的な4つ:
| パターン | 用語 | 内容のイメージ |
|---|---|---|
| 費用の前払い(前払費用) | 繰延処理 | 当期に支払ったが、サービスを受けるのが後期分が含まれているもの(例:家賃、保険料など) |
| 費用の未払い(未払費用) | 見越処理 | 当期にサービスを受けているが、支払が翌期になるもの(例:利息・家賃など) |
| 収益の前受(前受収益) | 繰延処理 | 当期に収益を受取または受け取る予定だが、サービス提供が翌期分が含まれるもの |
| 収益の未収(未収収益) | 見越処理 | 当期にサービス提供が終わっていて、収益発生しているが代金を受け取っていないもの(例:受取利息、受取手数料、家賃など) |

この中で今回の主役は「未払費用」と「未収収益」。「見越処理」のペアですね。
未払費用とは何か|簿記3級 決算整理で扱う“費用の未払い”
定義・意味
「未払費用」とは、すでにその期内でサービスを受けたり役務提供を受けたりしているのに、その代金をまだ支払っていない費用のことです。
- 負債に属する科目。
- 決算整理仕訳で「費用を費用計上」、相手に「未払費用」を貸方に計上。

つまり、「当期分の費用」だけど「支払いは後期に行われる」もの。
決算整理仕訳パターン・具体例
例えば、決算日が3月31日として、以下のような例を考えてみましょう。
例:利息について、1年後に支払う契約になっており、その期の3月31日時点でその年の利息の一部が未払いになっている。
- 決算整理仕訳(見越の処理)
(借)支払利息 ×円 / (貸)未払利息(未払費用) ×円 - 次期首(4月1日)に「再振替仕訳」をする必要あり。つまり決算整理で計上した未払費用をもとに次期の費用にする。
再振替仕訳について
- 再振替仕訳とは、決算整理仕訳を行った後、期首にその仕訳分を“元に戻す”処理。なぜかというと、決算整理仕訳は「当期の財務諸表を正しくする」ためだから。次の期に入ったら、その影響を持ち越さないようにこの再振替が必要。
- 未払費用の場合、「未払費用」の勘定を消して、期中費用に戻すような仕訳になる。
未収収益とは何か|簿記3級 決算整理で扱う“収益の未収”
定義・意味
「未収収益」は、当期中にサービス提供や役務の提供など収益の発生要件を満たしてるのに、まだ代金を受け取っていない収益です。
- 資産に属する科目。
- 決算整理仕訳では、収益を発生させる勘定科目を貸方、「未収収益」を借方に計上。

つまり、「当期分としてまだもらってない」が、「受取は後期に行われる」もの。
決算整理仕訳パターン・具体例
決算日が3月31日として、以下のような例を考えてみましょう。
例:会社が貸付金を持っていて、年利3%で利息が発生する契約。決算日が3月31日で、利息の受取りは翌年3月末。ただし、その期のうち、利息が少しだけ発生している。
- 決算整理仕訳(見越の処理)
(借)未収利息(未収収益) ×円 / (貸)受取利息(収益) ×円 - 次期首には再振替仕訳が必要。つまり「未収利息」を消して、収益の勘定に戻すような仕訳。
また、未収収益は“その他収益”・“受取手数料”など、収益の種類によって「未収○○」の名称になる。
試験ではその名称をきちんと読み取ることが大切。
未払費用と未収収益の違いを“わかりやすく”整理する
ここで、「未払費用」と「未収収益」を比べて、混乱しやすいところを整理します。
| 比較項目 | 未払費用 | 未収収益 |
|---|---|---|
| 費用 / 収益 | 費用 | 収益 |
| 資産 or 負債 | 負債 | 資産 |
| 発生しているかどうか | サービスを受けている etc. → 発生済み | サービスを提供済み etc. → 発生済み |
| 支払い/受取タイミング | 支払は後期(まだ支払ってない) | 受取は後期(まだ受け取ってない) |
| 決算整理仕訳で借方・貸方どちらか | 借方に「費用」、貸方に「未払費用」 | 借方に「未収収益」、貸方に「収益」 |
| 再振替仕訳が必要か | はい(期首で) | はい(期首で) |
覚え方のコツ・混同しやすいポイント
- “未”という漢字がついてる → 「まだされていない動き」がある(支払っていない/受け取っていない)
- 費用か収益かを最初に見極める → そこから「未払いか未収か」が決まる
- 肝は「お金の動き(支払・受取)」ではなく「役務の提供やサービスの実行/発生」のタイミング → 発生主義で考える
- 仕訳で「当期の損益計算書に含めるべきか」「貸借対照表にどの勘定科目で載るか」を想像する習慣をつける

払う Or もらうの見極めがキモ!
決算整理仕訳の問題で、未ときたらプラス(+)です。
試験でよく出る例と、簿記3級 決算整理仕訳で点数を取るためのポイント
よく出る例
- 利息の未払い → 決算日をまたぐ利息 → 未払利息(未払費用)
- 家賃、地代などサービス提供期間が決算日をまたぐもの → 前払/未払で調整
- 継続的なサービス提供に対する手数料を受けているが代金未受取 → 未収手数料(未収収益)
- 受取利息・受取配当など、受取日が期をまたぐ場合 → 未収収益
点を伸ばすための小技
- 問題文に「決算整理事項」「未払」「未収」「期間」などキーワードが出てきたらアラート。見落としが多い。
- 月数計算をきちんと。何かと“当期分”・“翌期分”の分ける月数でミスする人が多い。
- 再振替仕訳を「決算整理の次に来る」ものとして忘れがちなので、仕訳を書く場所を確保しておく。
具体演習問題で体で覚えよう!
せっかく理解したので、例題をひとつ。実際に手を動かすことで「わかりやすく」の理解がぐっと深まるから。
演習問題
決算日が12月31日、ある会社が貸付金を持っていて、年利6%で1年間貸し付けていた。利息は翌年3月末にまとめて受け取る契約。
貸付金の額は10,000円。決算日(12/31)時点で、当期に発生した利息を未収収益として計上する仕訳を示せ。
ヒント:利息の計算 → 10,000円 × 6% ×(12/12)=600円 (この契約なら「1年貸付」で決算日がちょうど年末なので当期は全部発生している)
答え例:
(借)未収利息 6,000円 / (貸)受取利息 6,000円
そして翌期首に再振替仕訳:
(借)受取利息 6,000円 / (貸)未収利息 6,000円
もし決算日が例えば9月30日なら、当期に経過した期間が9ヶ月なので、利息は 10,000 × 6% × (9/12)=450円 など計算するタイプの問題も出る。月数を数えるミスが命取り。
まとめ
「簿記3級 決算整理で未払費用と未収収益の違い」を理解するためのポイントを整理すると:
- 発生主義を理解することが基本。「サービスや役務提供」がいつあったかをまず見る
- 未払費用は“費用側の見越処理”、未収収益は“収益側の見越処理”という対比で考えると混乱しにくい
- 借方・貸方を仕訳で間違えないように、「費用 or 収益」と「支払/受取済みか未/後か」の2つを判断軸に持つ
- 再振替仕訳を忘れないこと(期首で)
- 問題演習を通して月数計算やキーワード(未払・未収・見越・繰延)に敏感になること

自信をもって、仕訳してください!!
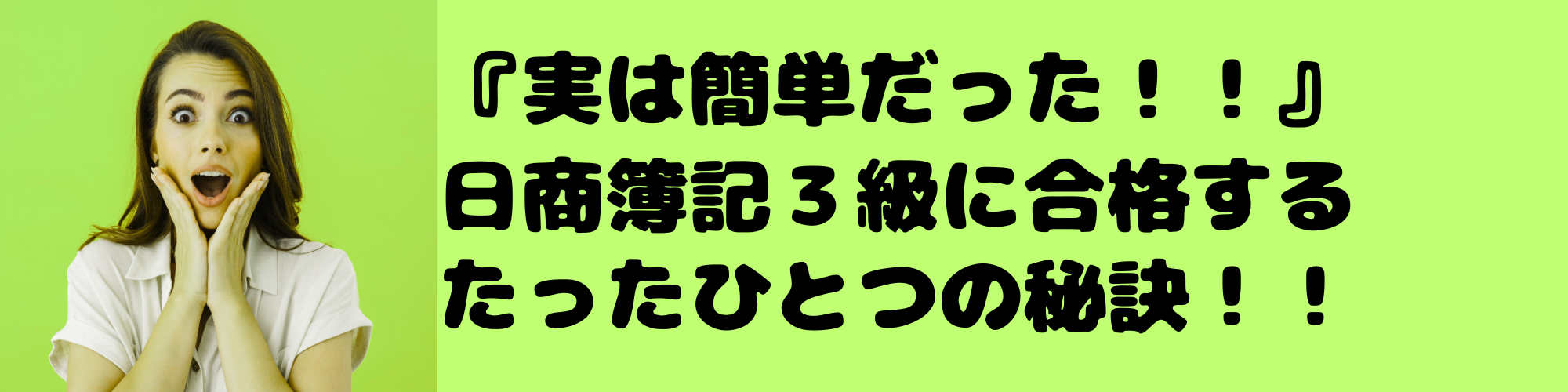
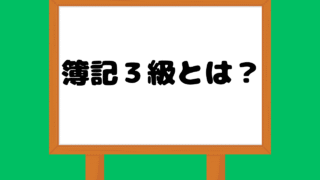
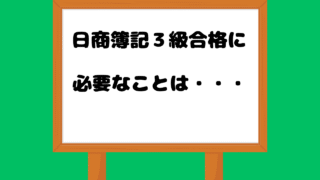
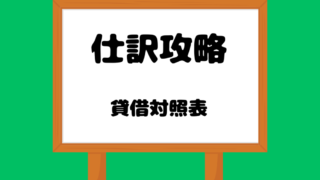
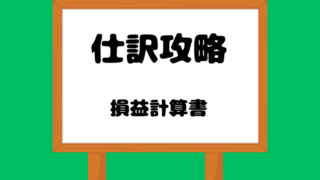
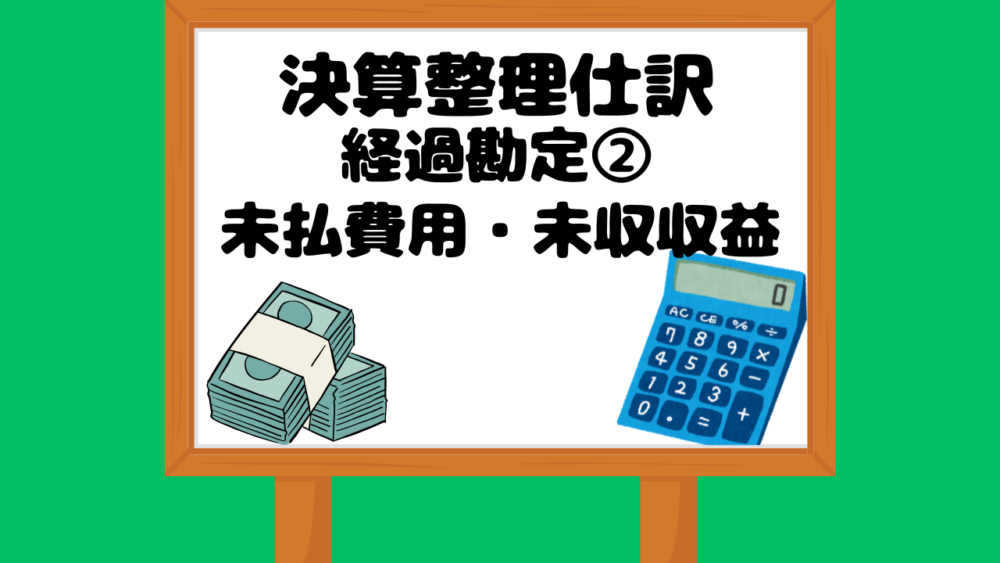

コメント