簿記3級の勉強で「減価償却累計額」っていう科目名を見た瞬間、「なんだこれ…?」と、違和感とともに困惑した人、多いんじゃないでしょうか。
正直、仕組みがピンとこなかったり、仕訳のイメージが湧かなかったりして、「難しい」と感じるのも無理ありません。
でも安心してください!
定額法の計算と間接法の仕訳さえ理解すれば、実はスゴくスッキリするんです。
この記事では、なぜ「簿記3級 減価償却累計額 難しい」と感じるのか、そのカラクリをざっくり解説します。
そして“3分でスッキリ”できるように、実例や図も交えて説明しますので、「あ、なるほど!」と納得できるはず。
減価償却累計額が難しいと感じるワケ
定額法のベースがイマイチ理解しづらい?
簿記3級で扱う減価償却費の計算って、定額法一択なんですが…これ、取得原価・耐用年数・残存価格って、一気に3つの数値を使うので、ちょっと頭がこんがらがるかも。
実務的には
「(取得原価-残存価格)÷耐用年数」
で出すんですが、これを「累計で積み上げる」ってなると、直感的にはわかりにくい人も多いですよね。
「間接法」と「累計額」がそもそも分かりづらい
簿記3級では減価償却の処理に「間接法」しか使わないので、直接資産額を減らす処理じゃなく、資産のマイナス科目である「減価償却累計額」で調整するんです。
これ、最初は「え?何で資産の横にマイナスが増えるの?」って、違和感ありますよね。

間接法が肝だね!!
帳簿価額って何? って混乱する
そしてこの累計額を使うことで、
「取得原価-減価償却累計額=帳簿価額」
という関係が成り立つんですが、この「帳簿価額」の概念がピンとこないまま次の処理に進むと、さらに混乱が広がります。

上記の通り計算すれば、資産が減少しているのと同じこと。つまり表現方法が違うだけだね。
この帳簿価額が、今現在の価値になるのか・・・ふむふむ。
3分でスッキリ理解するポイント
① 定額法ってこう考えよう!
取得原価(たとえば10万円)-残存価格(例:1万円)=減価償却費の対象(=9万円)。
これを耐用年数(例:3年)で割って、毎年3万円ずつ費用化していくイメージです。
覚え方は、「10万円が3年で1万円になる仕組み」と考えるとわかりやすいかも。
② 間接法を図で理解しよう
- 左側(借方)には「減価償却費」(費用)
- 右側(貸方)には「減価償却累計額」(資産のマイナス)
という形で仕訳します。
これにより、資産の取得原価はそのまま帳簿に残りつつ、経年分の「減った分」は累計額で表現します。
③ 式で覚えよう:帳簿価額の関係性
取得原価 - 減価償却累計額 = 帳簿価額
このシンプルな式を頭に入れておけば、「なんで取得原価が残ってるんだ…?」という疑問が消えます。実際の仕訳例で実感!
- 取得原価10,000円、耐用年数5年、残存価格10%、定額法で計算すると…
減価償却費=(10,000円-1,000円)÷5=1,800円
仕訳はこうなります:
(借方) 減価償却費 1,800円 / (貸方) 減価償却累計額 1,800円
これを年度ごとに積み上げていく感じですね。
まとめ
「簿記3級 減価償却累計額が難しい」と感じるのは、定額法での計算と“資産を直接減らさない”間接法の組み合わせが、直感的じゃないから。
でもここまで読んだあなたなら、もう大丈夫!
- 定額法のベースロジック:毎年同じ金額ずつ費用化 → 増減パターンが安定してると理解
- 間接法の仕訳構造:費用を借方、累計額で資産マイナスを貸方に仕訳
- 帳簿価額の公式:取得原価-累計=今いくら帳簿上残ってるかがわかる
この3つのポイントが腑に落ちれば、「あ、減価償却累計額ってそういうことか!」と、一気にスッキリします。
苦手意識がある人は、ぜひ上記の視点でノートに図を書いたり、声に出して説明してみてください。3分であの“モヤッ”が晴れますよ!

減価償却費・累計額の問題は、毎回試験で出るので、超重要!!
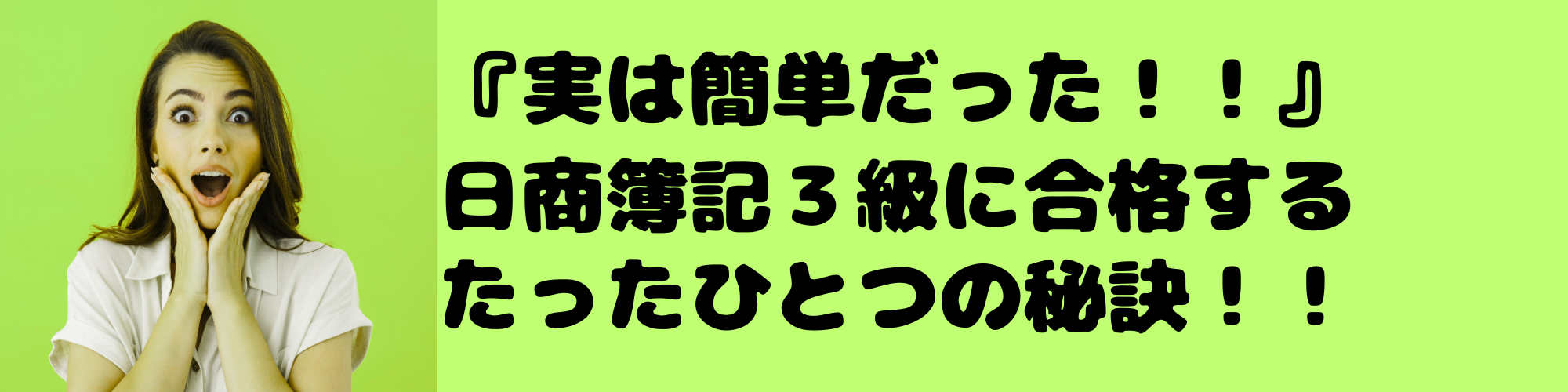
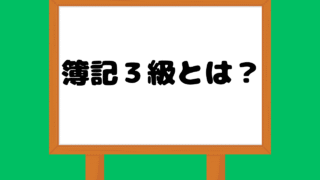
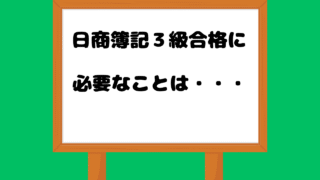
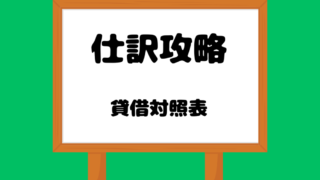
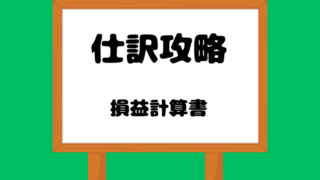
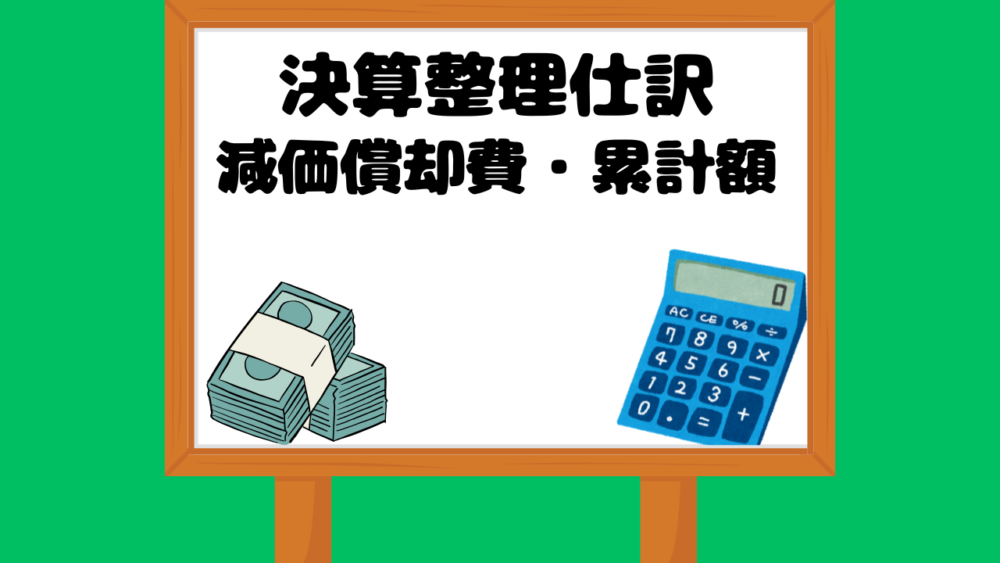


コメント