簿記3級の勉強、お疲れ様です!
おそらく、このタイトルにたどり着いたあなたは、今まさに「決算整理」という大きな壁にぶつかっているのではないでしょうか?
- 「決算整理って何のためにやるの?」
- 「減価償却費や貸倒引当金って、仕訳のルールが複雑すぎる…」
- 「問題文を読んでも、どうやって仕訳すればいいか分からない!」
こんな風に悩んでいませんか?
決算整理は、簿記3級の試験でも最重要論点の一つ。ここをマスターできるかどうかで、合否が分かれると言っても過言ではありません。
この記事では、そんなあなたの悩みをスッキリ解決するために、
決算整理の**「なぜそうするのか?」という根本的な理由から、「解き方のコツ」まで、簿記3級の初心者でもわかりやすく**解説
します。
簿記3級 決算整理って何?なぜ必要なの?
決算整理は、簡単に言うと**「会社の成績を正しく計算するための調整作業」**です。
普段、会社は取引が起きたタイミングで仕訳をしていますよね。
でも、期末(決算日)になってみると、まだ支払っていない費用や、受け取っていない収益など、お金の動きとタイミングがずれていることがよくあります。
このままでは、正確な会社の財政状況や経営成績がわかりません。
そこで、決算日という特別な日に、正しい利益を計算するための「最終調整」として行うのが、決算整理仕訳なのです。
この作業をすることで、会社の財産(資産や負債)が正しく表示され、当期に稼いだ利益(収益から費用を引いたもの)が正確に計算できるというわけです。
簿記3級の山場!決算整理の頻出項目をわかりやすく解説
決算整理にはいくつかのパターンがありますが、簿記3級で特に大事な項目は限られています。一つずつ、ポイントを絞って見ていきましょう。
減価償却費:資産の価値を正しく把握する
建物や備品といった固定資産は、使っていくうちに価値が下がっていきますよね。これを会計の世界で処理するのが減価償却です。
決算整理では、期末に「今期の価値の減少分」を計算し、費用として計上します。
【仕訳の考え方】
- 価値の減少分を計算する: 「取得原価 – 残存価額」÷「耐用年数」で1年分の減価償却費を計算。
- 費用を計上する: 減価償却費(費用)を借方に記入。
- 資産の価値を減らす: 資産を直接減らすのではなく、「減価償却累計額」という科目を使って、備品などの価値がどれくらい減ったかを貸方に記録します。

簿記の世界では、見た目・使用頻度に関係なく、価値は減少するよ!
貸倒引当金:将来の損失に備える
「売掛金」や「受取手形」は、将来お金を受け取る権利です。
しかし、取引先が倒産するなどして、回収できなくなるリスク(貸倒れ)があります。
貸倒引当金は、この貸倒れリスクに備えて、あらかじめ費用として計上しておくものです。
【仕訳の考え方】
- 将来の損失を見積もる: 期末の売掛金や受取手形の残高に対して、将来回収できなくなりそうな金額を見積もります。
- 費用を計上する: 「貸倒引当金繰入」(費用)を借方に記入。
- 将来の貸倒れに備える: 「貸倒引当金」という勘定科目を使って、貸倒れの可能性分を貸方に積み立てます。

リスクは付き物・・・。
経過勘定:費用のズレを調整する
「経過勘定」という言葉は難しそうですが、考え方はシンプルです。
たとえば、家賃を1年分まとめて支払った場合、その年の分だけを費用にしなければなりません。翌年分の家賃は、翌年の費用として計上する必要があります。
このような**「お金のやりとり」と「正しい費用の発生時期」のズレを調整**するのが経過勘定です。
経過勘定には、以下の4つの項目があります。
- 前払費用(先にお金を払ったけど、まだ当期の費用になっていない分)
- 前受収益(先にお金をもらったけど、まだ当期の収益になっていない分)
- 未払費用(当期の費用だけど、まだお金を払っていない分)
- 未収収益(当期の収益だけど、まだお金をもらっていない分)
これらの項目は、勘定科目の意味をしっかり理解して、ひとつずつ丁寧に仕訳をすることが重要です。

簡単な計算方法あるよ!!
決算整理仕訳は怖くない!プロが教える解き方のコツ
決算整理は、問題文を正確に読み解くことが合格への近道です。以下のステップを意識して問題を解いてみましょう。
- 問題文から論点を特定する:
- 「備品を取得した…」→減価償却費の問題
- 「売掛金残高に対して…」→貸倒引当金の問題
- 「家賃を1年分支払った…」→経過勘定の問題
- 決算整理前の残高を確認する:
- 決算整理前の試算表から、各勘定科目の残高を把握しておきましょう。特に貸倒引当金は、残高の確認が必須です。
- 変動する金額を計算する:
- 問題文の指示に従って、仕訳に必要な金額を正確に計算します。ここでの計算ミスが命取りになるので、電卓を落ち着いて叩きましょう。
- 仕訳を丁寧に行う:
- 計算した金額を、勘定科目の性質(資産・負債・純資産・収益・費用)を思い出しながら、借方・貸方に正しく記入します。

とにかく科目がどのグループで、定位置がどちら側かをしっかりと把握しよう!!
決算整理を早く正確に解くための裏ワザ
- 得意な論点から解く:
- 苦手な問題で時間を使いすぎないように、自分が得意な論点から先に解いていきましょう。
- 勘定科目をメモする:
- 計算用紙に、仕訳をメモしてから解答用紙に記入するとミスが減ります。
- 「なぜ?」を意識する:
- 「なぜこの仕訳をするんだろう?」と常に考えることで、単なる丸暗記から脱却し、応用力が身につきます。
まとめ|簿記3級の決算整理を乗り越えて合格へ
簿記3級の決算整理は、確かにわかりやすくはないかもしれません。
でも、この記事で解説したように、
**「なぜ?」という理由を理解し、「解き方のコツ」**を掴めば、
決して乗り越えられない壁ではありません。
- 決算整理は**「会社の成績を正しく計算するための調整」**
- 頻出の論点(減価償却費、貸倒引当金、経過勘定)を重点的に対策する
- 「論点特定」「残高確認」「金額計算」「丁寧な仕訳」の4ステップで解く
この3つのポイントを意識して学習を続ければ、必ず決算整理をマスターできます。
焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。あなたの簿記3級合格を応援しています!

詳しい解説は、次回から。お楽しみに!!
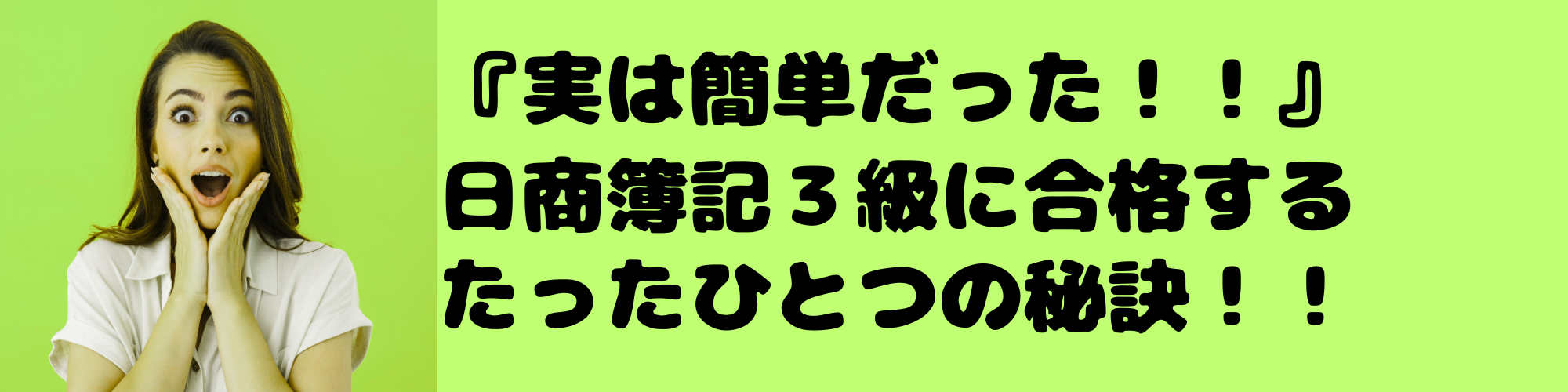
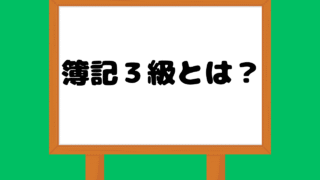
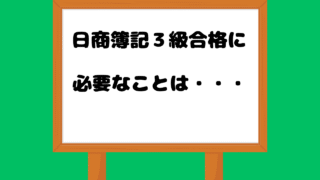
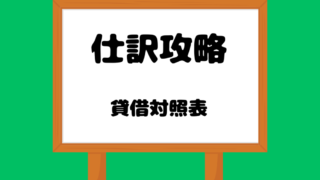
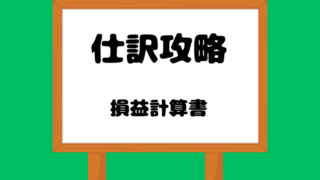
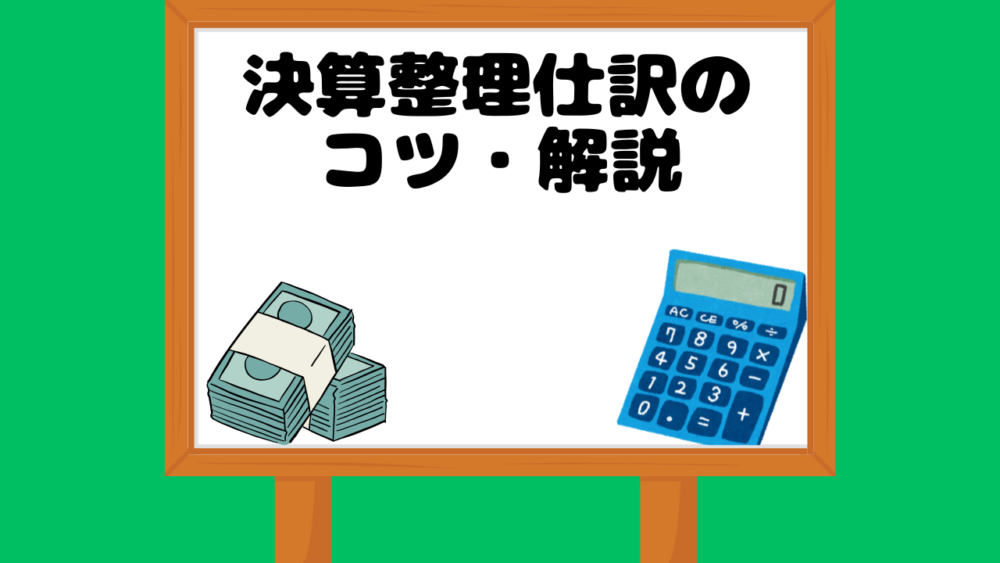


コメント