簿記3級で「貸倒引当金」と聞くと、「これ何?どうやって計算して仕訳するの?」って混乱しちゃいますよね。
でも安心してください。
この記事では、簿記初学者でも「なんとなく分かる」を「しっかり分かる」に変えるために、計算方法と仕訳のコツを3分でサクッとまとめていきます。
まずは「貸倒引当金」って何?ざっくり解説
貸倒引当金って実は、 “いつか回収できなくなるかもしれない金額を見積もって、当期の費用として先に計上する” 仕組みなんです。
こうすることで、収益と費用をちゃんと同じ期間に対応させる「費用収益対応の原則」に合っちゃう。
つまり、「今」は困ってないけど、将来のリスクに備えて「保険」をかけておくイメージですね。
また、貸倒引当金は貸借対照表では「売掛金などの資産-控除項目」として表示される、評価勘定という特殊な扱いですよ。

万が一、相手から売掛金を回収することができなくなった場合・・・考えたくないです。
計算方法と仕訳の流れで押さえる
簿記3級で出る 計算方法はコレ!
簿記3級では、売掛金(売上債権)の期末残高に対して、問題文で与えられる「貸倒設定率」を掛けて計算するのが一般的。
問題文に設定率が書いてあるので、過去のデータを出したりはしません 。
計算式はめちゃ簡単:
- 貸倒見積額 = 売掛金 × 貸倒設定率
仕訳は「差額補充法」が基本!
簿記3級で主に使われるのは「差額補充法」です。
差額補充法のポイント:
- まず計算:貸倒見積額を出す
- 現在の貸倒引当金残高と比較
- 残高が少なければ「不足分を繰入」、多ければ「余分を戻入」する仕訳をする
例えば、
売掛金50,000円、設定率3%、現残高1,000円の場合
→ 必要額は1,500円、差額は500円なので
「(借方)貸倒引当金繰入 500 /(貸方) 貸倒引当金 500」
逆に現残高が2,000円だったら余分な500円を戻して
「(借方)貸倒引当金 500 /(貸方 貸倒引当金戻入 500」
実際の「仕訳パターン」をケース別に整理
① 設定額が残高を上回る(繰入)
- 売掛金残高 × 設定率で計算 → 当てはまる金額と現残高を比べる
- 不足分を「貸倒引当金繰入(費用)」と「貸倒引当金(評価勘定)」で仕訳
例:繰入額=200円 →貸倒引当金繰入 200円 / 貸倒引当金 200円
② 設定額が残高を下回る(戻入)
- 余分な残高分を減らすために「戻入」の仕訳を。
例:戻入額=100円 →貸倒引当金 100円 / 貸倒引当金戻入 100円
③ 実際に貸倒れ発生時(引当金あり)
- 実際売掛金が貸倒れた時、すでに引当金で費用化してるから、評価勘定から減らすだけ。
- 例:貸倒れ額200円 →
貸倒引当金 200円 / 売掛金 200円
④ 実際に貸倒れ発生時(引当金なし)
- 引当金設定していない債権が貸倒れたら、費用として直接計上。
- 例:貸倒れ額200円 →
貸倒損失 200円 / 売掛金 200円

貸倒損失は、引当金以上の債権が発生した場合にも、出てくるよ!!
まとめ:混乱しやすいポイントはココ!
- 計算自体は簡単(売掛金 × 設定率)だけど…
- 差額補充法の「差額比較」と「繰入/戻入の判断」がポイント
- 「引当金あり」の場合と「なし」の場合で処理が全然違うのも要注意!
- 表示は貸借対照表で「売掛金-貸倒引当金」と評価されます。
最後にもう一度おさらい:
- 売掛金の期末残高 × 設定率 → 見積額(必要な引当金額)
- 現残高との差額で「繰入」or「戻入」を判断
- 実際に貸倒れがあった場合は、引当金の有無で仕訳が変わる!
これを頭に入れておけば、簿記3級の貸倒引当金、マジで怖くないですよ。応援してます!

計算自体はとても簡単。仕訳だけ間違わないようにしないと!!
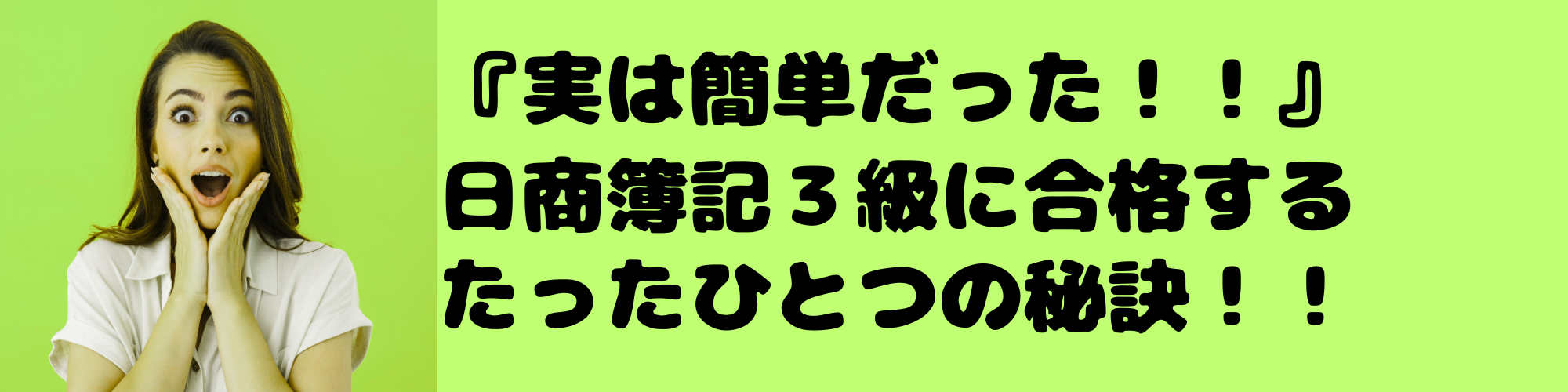
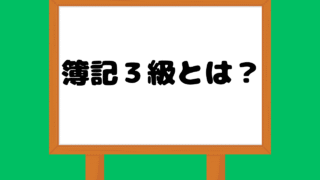
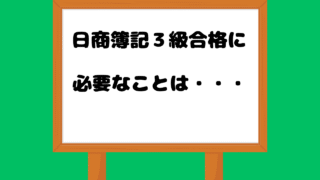
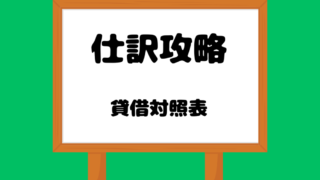
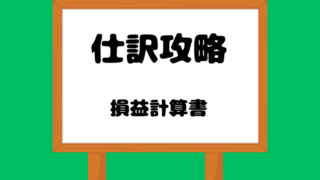
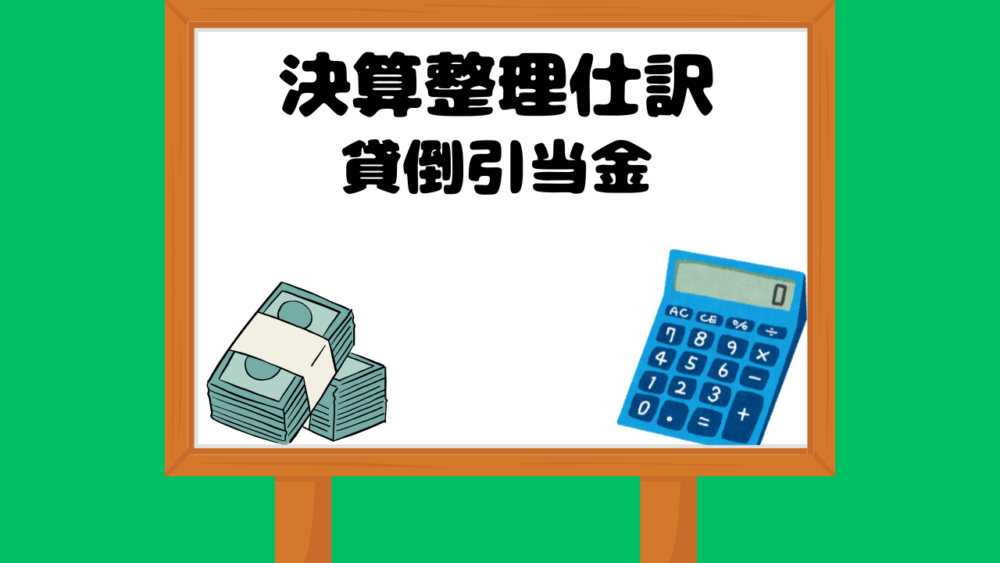


コメント