
- 今回のポイント!
- 収益勘定とは、会社がビジネス活動を通じて得る収入を記録するための勘定科目です。
- 「収益」とは、単にお金が入ってきたことを意味するのではなく、会社の本業や副業から得られた対価 を表します。
- 損益計算書では「収益の部」に表示され、最終的に利益計算に反映されます。


- 主に収益勘定は、貸方(右側)が定位置です。
- 貸借対照表同様に、勘定科目がどのグループで、定位置がどちら側かを、しっかりと把握。
「簿記3級を勉強し始めたけど、収益勘定って言葉が出てきて、急に難しくなった…」
こんなふうに感じているあなた、大丈夫です!収益勘定は、簿記の世界の基本であり、会社の儲けを記録するために欠かせない勘定科目です。
私たちの日常生活でいう「収入」や「儲け」と同じようなものだと考えれば、意味も使い方もスッキリ理解できます。
この記事では、収益勘定の意味と、簿記3級で学習する代表的な勘定科目を、初心者でもスッと頭に入るようにわかりやすく解説します。
主な収益勘定の種類(簿記3級で登場するもの)
- 売上 商品販売の代金収入・商売の中心となる本業の収益
- 受取手数料 サービスの提供や事務手続きの代行などで得た手数料収入
- 受取家賃 不動産や設備を貸して得た収入
- 受取利息 預金や貸付金などから発生する利息収入
- 受取配当金 株式などの投資から受け取る配当金
これらはいずれも会社にとって「収益」として処理されます。
収益勘定の特徴
- 発生主義で計上 → 実際に現金を受け取った時ではなく、「収益が発生した時点」で記録します。
- 貸方記入で増加 → 簿記では、収益勘定は貸方(右側)に記録すると増加します。
- 損益計算書に反映 → 最終的に「収益-費用=利益」となり、会社の成績を表します。
簿記3級でなぜ重要?「収益勘定」の勘定科目の意味
収益勘定とは、会社が事業活動を通して得た、すべての儲けを表す勘定科目の総称です。
簿記3級では、主に以下の3つの勘定科目が収益勘定として登場します。
- 売上: 会社の本業である商品を販売して得た儲け。
- 受取利息: 預金や貸付金から得た利息。
- 受取手数料: 仲介や代行のサービスを提供して得た手数料。
これら3つは、すべて「儲けが増える」という共通点があります。
そのため、仕訳では貸方に記入するというシンプルなルールがあります。
「収益勘定」の具体的な仕訳パターン
収益勘定の意味を理解するには、実際に仕訳をしてみるのが一番の近道です。
ここでは、代表的な収益勘定の取引例を見ていきましょう。
「売上」の仕訳例
会社の本業で最も重要な収益勘定です。商品を販売し、代金を受け取った場合に売上が発生します。
- 取引例1: 商品100,000円を販売し、代金を現金で受け取った。
この取引では、現金という資産が増え、売上という収益が増えました。
| 借方 | 貸方 |
| 現金 100,000 | 売上 100,000 |
「受取利息」の仕訳例
会社が預金している銀行から利息を受け取ったり、他社に貸し付けたお金から利息を受け取ったりした場合に受取利息が発生します。
- 取引例2: 銀行預金の利息1,000円が普通預金口座に入金された。
この取引では、普通預金という資産が増え、受取利息という収益が増えました。
| 借方 | 貸方 |
| 普通預金 1,000 | 受取利息 1,000 |
「受取手数料」の仕訳例
会社が商品を販売するだけでなく、他社の商品の仲介をしたり、サービスの代行をしたりして手数料を受け取った場合に受取手数料が発生します。
- 取引例3: 委託販売の仲介手数料として、現金5,000円を受け取った。
この取引では、現金という資産が増え、受取手数料という収益が増えました。
| 借方 | 貸方 |
| 現金 5,000 | 受取手数料 5,000 |
収益勘定の勘定科目を効率よく覚える3つのコツ
ここまで「収益勘定」について見てきましたが、簿記3級には他にもたくさんの勘定科目が出てきますよね。
すべてを丸暗記するのは大変ですが、いくつかのコツを押さえれば、効率的に学習を進めることができます。
コツ1:仕訳のパターンで覚える
勘定科目の意味を一つずつ覚えるのも大切ですが、それだけでは頭に残りにくいもの。
「儲けが増えたら、収益勘定を貸方に記入する」
というシンプルなルールを仕訳のパターンと一緒に覚えることで、勘定科目がどのように使われるかを身体で覚えることができます。
コツ2:5つのグループを常に意識する
すべての勘定科目は、資産・負債・純資産・収益・費用の5つのグループのどれかに必ず分類されます。
- 収益勘定は、この中でも「儲け」を表す特別なグループです。
- 収益が増えると、会社の利益が増えるので、貸方に記入します。
このように、5つのグループを常に意識しながら学習を進めることで、勘定科目の使い分けが簡単になりますよ。
コツ3:「本業かどうか」を考える
簿記3級で似たような勘定科目が複数出てきたら、まずは「これは本業の儲けかな?それとも本業以外かな?」と考える癖をつけましょう。
- 売上 → 本業の儲け
- 受取利息・受取手数料 → 本業以外の儲け
このシンプルなルールを適用するだけで、収益勘定の使い分けがより明確になります。
まとめ:収益勘定は怖くない!
簿記3級の学習において、収益勘定は会社の儲けを理解するための基本です。
この記事で解説したように、収益勘定は「儲けが増える」という共通点があり、仕訳では貸方に記入するというシンプルなルールを理解すれば、決して難しいことではありません。
一つひとつの勘定科目を丁寧に理解し、仕訳の練習を繰り返せば、必ず簿記3級の合格に近づけます。

おさらい
「儲けが増えたら、収益勘定を貸方に記入する」
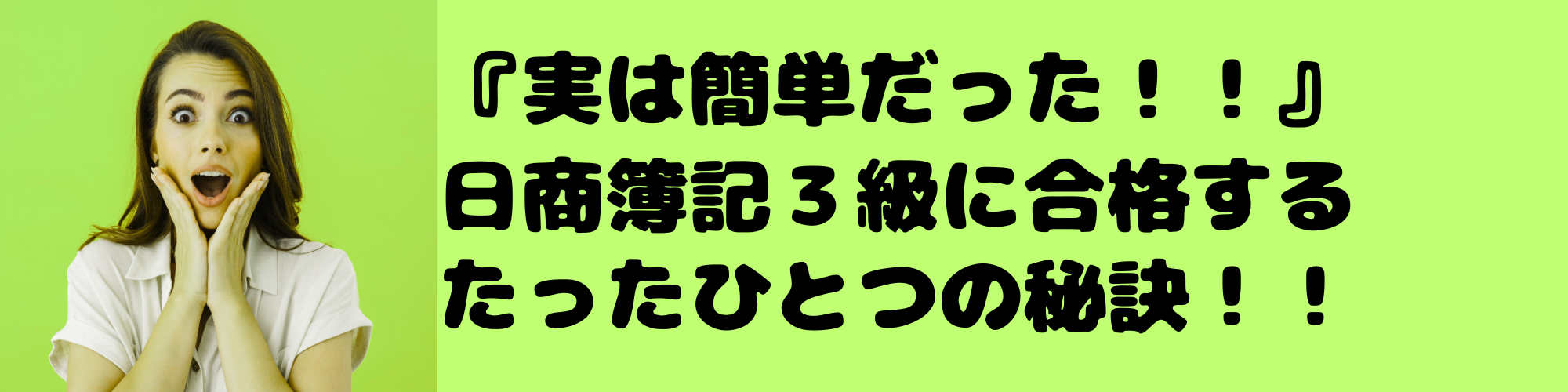
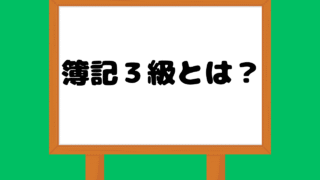
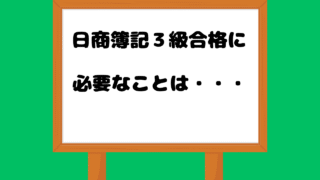
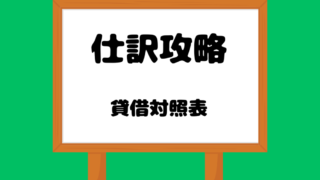
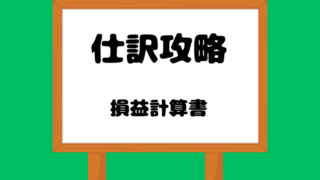
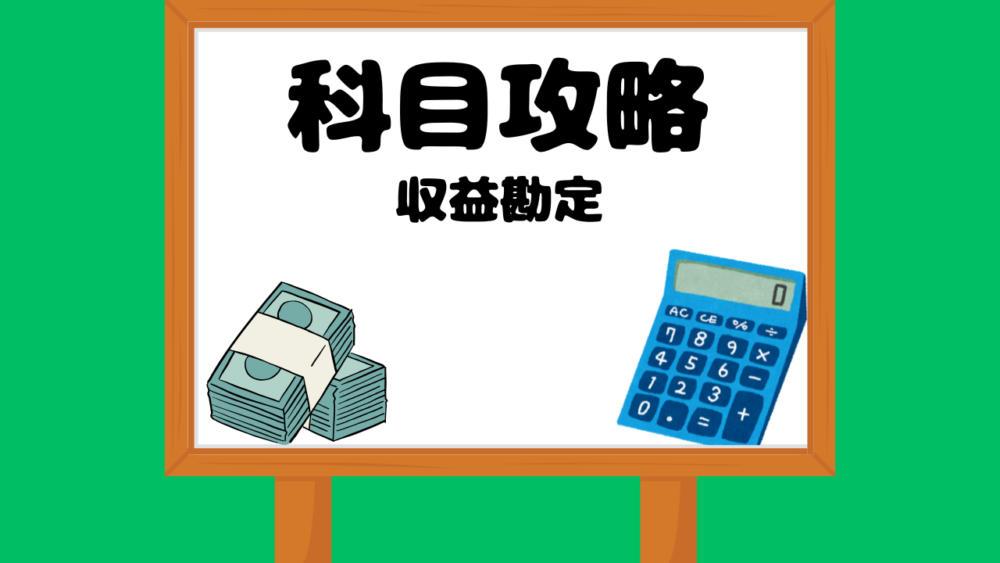


コメント